
あたふたしてるよ!
入院の数日前から実家に身を寄せていた。入院の当日は義兄の運転する車で病院まで送ってもらう。姉も同行してくれた。
実家から病院までは、車で片道1時間ほどだ。
姉と義兄には、この後何回も病院に通ってもらうことになる。
ホンとすみません。足を向けて寝られません。
入院初日は大部屋に空きがないということで個室へ案内された。
差額ベッド代の問題で、わたしが入るのを断念した個室だ。
病院側の都合なので個室代は不要だという。
「ラッキー。幸先がいい」とわたしは喜んだ。
K病院の個室は驚くくらい広かった。わたしが借りている1Kの部屋より広いのではなかろうか。
洗面所はおろかトイレもシャワーもある。貧乏性のわたしにはこの広さと静かさが落ち着かない。さすが1日○円かかるだけのことはある。
あまりの広さと静かさに、個室に入って2日目には、大部屋のほうがいいかもと思うようになってしまった。
まあ手術の翌日からは大部屋に入ることになったのだから、この時点で「わたしは個室にいても落ち着かない」と気づいていたのはよかったかもしれない。
大部屋は大部屋でいろいろとあるのだが、最初に個室を経験していたことで、大部屋にいることを不満に思うことはなかったのだから。
この広い個室で、わたしは手術日の木曜の朝まで過ごすことになる。
月曜の午後の入院だったが、入院手続きをして部屋に荷物を置いた後はさっそく検査になった。
翌日の火曜も検査につぐ検査。
翌々日の水曜は予備日ということで、検査はなし。術前説明会があったくらいか。
最初のMRI検査から入院までに日が空いていたので、入院の半月ほど前に、わたしはK病院の系列の病院で会社の健康診断を受けていた。
が、果たしてあれは必要だったのかと思うくらい、入院した後は検査を受けまくった。
印象に残っている検査がある。造影検査を受けたときだ。
腕に刺して固定していた留置針から検査用の液体を入れた。
検査技師から「体が温かくなります」と言われ、本当にすぐ体が温かくなった。
『温かいなにか』が、手の先から足先、果ては肛門まで巡っていくのがわかる。
血管って体中に巡らされているんだな、と改めて実感した。
手術前日に術前説明会を受ける
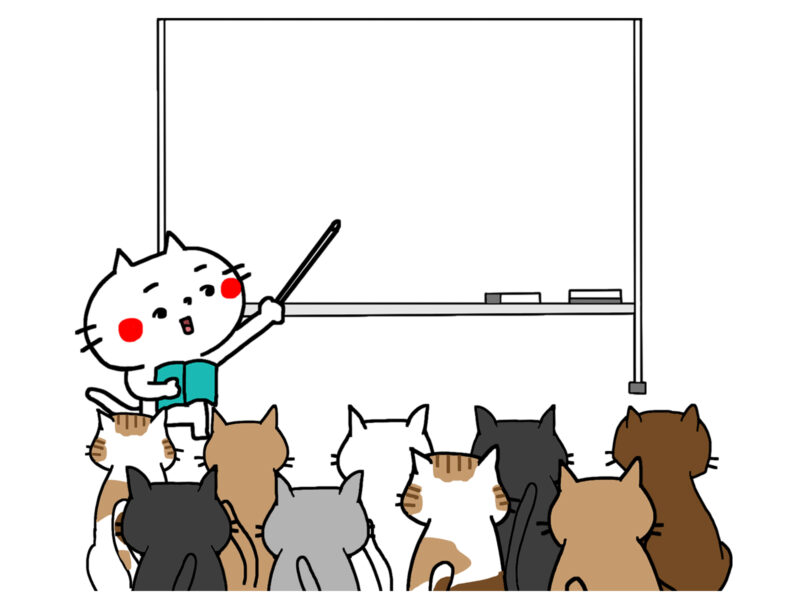
H医師による術前説明会を受ける
座ったまま貧血を起こしそうになる
手術前日には、家族を交えての術前説明会が予定されていた。執刀するH医師に、手術についての詳しい話をしてもらうのだ。
術前説明会には姉と義兄に同席してもらう予定だった。
だが看護師から、それ以外の家族の同席もお願いしたいと言われた。
姉と義兄だけではダメなのかと訝るわたしに、
「なるべく多くの家族や親族のかたにお話を聞いていただきたいと先生がおっしゃっているのです。大きな手術になるからと」
看護師の声音は静かだったが『大きな手術』という言葉が、今更ながら背中にのしかかった。
だがしかし、これは困った。高齢だわ要介護だわの親は無理。となると、下の姉に声をかけないといけない。
ちなみにわたしは3姉妹の末っ子だ。これまでに何度も書いてきた姉と義兄というのは、上の姉夫婦のことだ。
ここでひとつ問題があった。
入院前後は実家に身を寄せる予定だったこともあり、実家で親と同居している上の姉夫婦には病気のことを詳しく話していた。
が、下の姉には曖昧なことしか話していなかったのだ。
下の姉も近くに居を構えているが、下の姉には下の姉の家族がいるわけだし、わたしのことで心配させたり気を遣わせたりするのもなあ、と思ったのだ。
けして病気の説明をするのが面倒だったわけではない。ええ、けして。
黙っているわけにもいかなくなったわたしから、手術直前になって、実は病気は脳腫瘍です、と聞かされた下の姉は驚いたようだ。
電話越しでもわかるくらい声がひっくり返っていた。
「あんた、たいした病気じゃないって言ったやん!」
言いましたか。言いましたね。病名も言ってませんでしたもんね。
驚きつつも、下の姉は、翌日の術前説明会への同席を快諾してくれた。
説明会の時間が夕方なので、仕事を抜けてくるという。(幸いというか、下の姉の仕事先が病院の近くだった)
ありがたや。下の姉にも足を向けて寝られません。
手術前日の説明会には、上の姉夫婦と下の姉が来てくれることになった。
執刀医のH医師による説明会は、数人の医師や看護師も同席して行われた。今後担当医になるK医師もこのとき同席していた。
H医師の説明は、あたりまえなのだが、最悪を想定した話だった。
どのような内容の手術になるか、術中に起こるかもしれないこと、術後に起こるかもしれない合併症や感染症、後遺症の話。
H医師のホワイトボードに書きながらの説明は、図解入りで丁寧でとてもわかりやすかった。
あまりのわかりやすさに、なまじ人より多めの想像力が刺激されて血が引いてしまい、椅子に座ったまま貧血を起こしてコケそうになった。
じわじわと緊張が強くなってきたが、
「でもそれって最悪の場合でしょう、あははっ」
下の姉が、わたしの緊張を笑い飛ばしてくれた。
お、オネーチャン、わたしはあなたのそういうところが好きだよ。
説明会が終わった後、下の姉は仕事に戻っていき、上の姉夫婦とわたしは病室に戻った。
説明会の前に部屋の荷物をまとめていたのだが、まとめ忘れたものがないかチェックする。
なぜ荷物をまとめていたのかというと、翌日の手術日の朝には個室を空にしなければいけなかったからだ。
手術日の夜はICUに入ることが決まっていたし、その後に入る一般病棟の部屋がどこになるかはまだ未定だ。
まとめた荷物は、義兄の車のトランクに入れておいてもらうことにする。
手元に置いておくのは、小さなバッグに入るくらいの手回り品と、ICUに持ち込むタオルなどの荷物だけだ。
姉夫婦が帰った後は、必要最小限のものしかない広い個室は、なお広く見えた。
いよいよ手術
手術前夜に検温に来た看護師のお姉さんは、顔見知りになった人だった。
笑顔の優しい看護師に、明日手術ですね、と聞かれ、はい、と答える。
お姉さんは、頑張ってくださいね、とハグしてくれた。
あの、泣きそうなんですけど。
手術前夜は静かに更けていった。
手術当日の朝、わたしはすごく喉が渇いていた。
病院内は乾燥しているのでただでさえ喉が渇くのに、前夜から絶飲食をしていたからだ。
うう、喉が渇く。水が飲みたい。
朝、検温に来た看護師に「すごく喉が渇くんです」と訴えたら「じゃあ、うがいしてください」と言われてしまった。
うがい。喉が渇いたから、うがい。
今のわたしなら「パンがないならお菓子を食べればいい」と言われたどこかの市民の気持ちがよくわかる。
しかたないので、何度もうがいをして乾きをごまかした。
朝の早い時間に姉夫婦が病室に姿を見せた。
今日は手術が終わるまで家族用の控え室だか待合室だかで待ってもらう予定だ。(病室は空けないといけないのでいることができない)
手術中は常に家族の誰か、少なくともひとりは院内にいないといけないらしい。
待ち長くなるだろうと思うと申し訳ない。
術衣に着替え、点滴をしたまま歩いて手術室へ向かう。
姉夫婦とは、病室のある階のエレベーターホールで別れた。
頑張れ、と姉がガッツポーズを作る。わたしは、うん、とうなずいた。
エレベーターを下り、方向音痴のわたしにはどこをどう歩いたのかわからないうちに、手術室のあるフロアに入る。
がらりと雰囲気が変わった。
しんと静かな空気、メタルチックな廊下や扉。
医療ドラマでよく見る光景だ。カラカラという、わたしが点滴スタンドを押す小さい音だけが響く。
「……ドクターX」
思わず呟いたら、わたしにつきそって歩いていた看護師が、くすりと笑った。
目の前で手術室の扉が開いた。
据えられた手術台。手術台を照らしているのは無影灯だ。
忙しく立ち働いているスタッフたち。
姿を見せたわたしに、スタッフは皆穏やかに話しかけてくれる。手術前の緊張をほぐそうという気配りなのだろう。
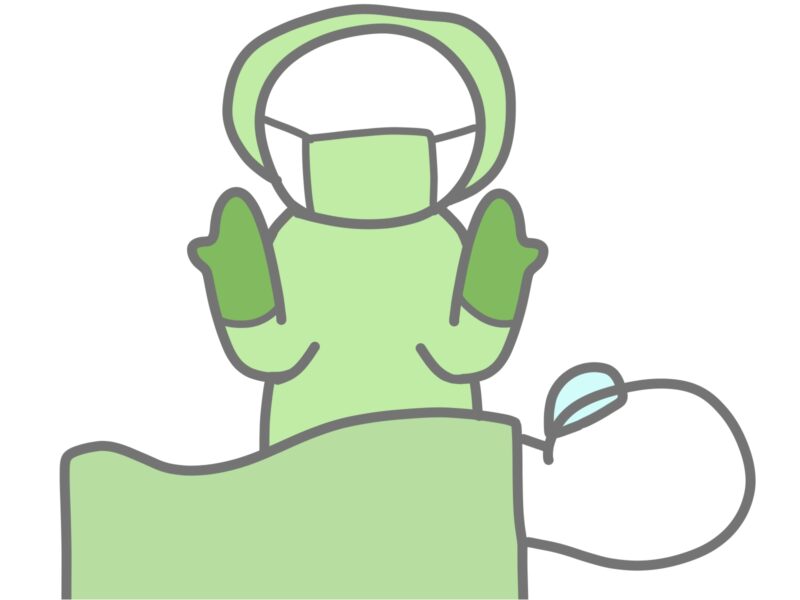
いよいよ手術当日
手術台に横になってなお、まだどこか現実感が薄い
手術台の上に横たわる。こんな状態なのに、まだどこか現実感が薄い。え、今から手術を受けるんだっけ? という感じ。
鼻と口を覆うように、カプセルめいたマスクがかぶせられた。
「これは麻酔ではないです。きれいな空気が出てきます」
説明するのは麻酔医だ。手術の数日前に病室へ来て、全身麻酔についての丁寧な説明をしてくれた。ここの医師は皆説明上手だ。
今何時だろうか、とふと思う。朝の9時には病室を出たはずだから、9時過ぎというところだろうか。
「では点滴でお薬を流しますね」
麻酔医が続ける。その後は記憶にない。眠いと感じた意識すらない。
全身麻酔ってすごい。
体感時間ではものの5分ほどしか経っていないと思うのだが、
麻酔医が、ぽんぽんとわたしの肩を叩いていた。
「手術が終わりましたよ」
終わったの? 5分しか経っていないのに?
「今は夕方の7時です」
しちじ? えーと、しちじって何時?
まだ意識が朦朧としていたので、うまくものを考えることができない。
知らない間にずいぶん時間が経っていたらしいことはわかった。
姉と義兄は待ち長かっただろうな、と次に思った。
ICUで迎えた夜は
ストレッチャーに乗せられたまま、手術室からICUへ運ばれた。
ひどく寒かった。自分の体ががたがたと震えているのがわかる。
体の上に布団らしきものが掛けられているのがわかるのだが、それでも寒くて震えが止まらない。
「……寒い、寒い」
わたしの呟きが聞こえたのか、そばにいた誰かが「震えているから、もっと……」と指示している声がぼんやりと聞こえた。
体を覆うものが増やされて、ようやくほっと力が抜けた。
ICUに移ったときに、少しだけ家族と面会ができるとあらかじめ言われていた。
姉の声が聞こえて、薄く目を開ける。
姉と義兄の顔が見えた。後で聞いたら、下の姉も駆けつけていたらしい。ごめん、気づかなかったよ。
「手術は終わったよ。よく頑張ったね」と姉が言う。
涙があふれるのがわかった。
あ、涙が、と姉が言い、しかし手術後のわたしに触れていいのかとためらっている気配がして、そばについていたスタッフが涙を拭ってくれた。
短い面会時間はすぐに過ぎ、
「また明日来るからね」
姉の言葉にうなずいた。
翌日の午後までICUで過ごしたが、あまりにも苦しい記憶で、思い出すのがしんどい。
あんなに長い一夜を過ごしたのは後にも先にもあのときだけだ。
両腕には点滴、胸には心電計、両足には血栓を予防するというフットポンプをつけられていた。
手術の間同じ体勢でいたからか、とにかく体中が痛かった。
寝返りを打っていい、と言われていたのがせめてもの救いか。
「頭には点滴をしていないから寝返りしていいよ」という医師の言葉をうっかり聞き流してしまったが、頭に点滴ってなに? それしてたら寝返りもできなかったの?
震えるほどの寒さは治まっていたが、今度は体を覆う布団が重くて暑い。
ずっしりと体にかかる重みが苦しくて、なんとか布団をずらそうとするのだが、腕がうまく動かない。体も動かない、とにかく痛い。苦しいのに自分ではどうすることもできない。動かない体がもどかしく、恐怖すら感じた。
スタッフが様子を見に来たときに(この夜は頻繁に誰かが様子を見に来てくれた)布団が重いのでずらしてほしい、と訴えた。
もう寒くないですか、と聞かれてうなずいたら、布団が1枚はずされた。体の上から重みが減ってほっとした。
ほっとはしたが、体の痛みがひいたわけではない。
右を向いても仰向けになっても左を向いても体が痛い。
特に首と腰が痛い。
わたしは左の後頭部を開頭したので、おそらく手術中は体の左側を上にした体勢で固定されていたのだろう。
後で気づいたが、右側の腰あたりに鬱血ができていた。この鬱血、つまりあざがベッドにあたるたびに痛い。
数分と同じ姿勢を保つことができず、ひっきりなしに寝返りを打つ。
もちろん寝返りを打っている間も体が痛い。左側を下にしたら頭が痛くなるし、右側を下にしたら腰の鬱血が痛い。
痛い痛い、とうめきながら左向きから仰向け、右向き、また仰向け、左向き、と往復しても6分しか経っていない。
ICUの壁は時計が掛けられていて時間を見ることができたのだが、この時計の針がまったく進まない。
10時間ほどをほぼ体感することなく過ごしたわけだが、どこかに余計なお世話の神様でもいるんじゃないかと思った。
その神様が「なんと、知らない間に10時間も失ってしまったのか。よしわかった、ICUにいる間に失った分の時間を取り戻させてやろう」とでもおっしゃりやがったんではないか。そうじゃなければ、こんなにも時計の針が進まない理由が思いつかない。
ひどく喉が渇いて痛かった。ひゅーひゅーと自分の喉から息が漏れているのがわかる。
口中から喉の奥の奥まで、からからに乾いていた。
もしあの一晩を眠ることができたなら、わたしはきっと、水を求めて砂漠をさまよう夢を見ていたことだろう。
夜になってからも看護師が様子を見に来てくれたので、
「喉が渇いた」と出ない声で訴えた。
「じゃあ、お水を含ませましょうね」と、スポンジのついた歯ブラシのようなものに水を含ませて唇や歯茎を拭ってくれる。(名称は、まんま『口腔ケア用スポンジブラシ』らしい)
水はまだ飲むことができなかった。
唇や歯茎を拭ってもらうと一瞬潤った気になるが、あっという間にまた乾く。喉はからからのままだ。
この夜は、看護師が来るたびに水を含ませてもらった。
わずかに湿った唇をなめながら、水が飲みたい、とひたすら思っていた。
永遠に明けないのではないかと思うくらい、あの一夜は長かった。
もうICUには入りたくない。というか、ICUに入るような状態になりたくない。
ところで長い長い夜が明けた翌朝、わたしは看護師に2人がかりで清拭をしてもらった。清拭というのは、ベッドに横になったまま体を清めてもらうことだが、それをしてもらったのはICUで迎えた朝の1回きりだ。
まだ幾分朦朧としていたので、そのときはされるがままだったのだが、正気に戻った今なら思う。切実に思う。
看護師のお姉さんにオシモを流してもらうっていたたまれない!
いや看護師の仕事は立派だ。ただただ頭が下がる。どれだけ感謝しても足りない。
しかしわたしはここに誓おう!
わたしは一生、オシモを自分で洗える体でいるために努力をすることを!
ICUで迎えた朝
えーと、話を変えよう。
手術の翌日、朝のうちには体を起こす練習を始めた。
まだ体中が痛い。不思議と頭はそんなに痛くない。つっぱったような感じがするだけで。
最初は自分で体を起こすことができなかった。
手助けしてもらって体を起こし、ベッドに座る。
「水を飲む練習をしましょう」と言われて喜んだ。
その日は金曜だったが、水曜の夜からなにも口にしていない。
喉はずっとからからのままだ。
飲んでいいんですか、と聞こうとした声がほとんど音にならない。
手術中は人工呼吸器をつけていたと聞いた。(意識が戻ったときは、すでにチューブは口からはずされていた)
麻酔から目が覚めてからずっと、喉になにかが絡まったような詰まったような感じがして呼吸が辛かったのだが、チューブ挿入の影響で喉だかどこだかを痛めたらしい。
嚥下練習をするとかで、看護師がベッドに座ったわたしの口の中に、針のない注射器をさし入れる。
「少しだけ水を入れます。ゆっくり、ごくん、としてみてください」
待ちに待った水が、少しずつ口の中に入ってくる。
飲みこもうとして、わたしは困った。
水を飲みたいのに、そりゃもうとても飲みたいのに、飲みこみたくない。
口中のわずかな水を、飲み下せる気がまったくしなかった。
「はーい、ごくん」
促されて、ごくん、となんとか喉を動かすが、見事に噎せた。苦しい。
水に少しずつとろみをつけて、何度も飲みこむ練習をする。
何度も噎せた。なんとか飲みこめるようになったのは、水にかなりとろみをつけた後だ。
液体に噎せるという状態は、この後10日ほども続いた。
入院中の飲み物はもっぱらお茶だったが、その間はずっと、とろみ剤を使ってお茶にとろみをつけていた。(最初の数日は食事の味噌汁にもとろみをつけた。かなり微妙な味だった)
冷たいお茶にとろみをつけると劇的に美味しくない、という嬉しくない発見もした。
だいたい冷たいお茶にはとろみ剤が溶けにくい。溶け残ったとろみ剤の小さい塊が、また劇的に美味しくない。
ようやっととろみをつけずに水が飲めるようになり、姉夫婦に差し入れてもらって飲んだ冷たい爽健美茶が喉に沁みいるほど美味しかった。
話をICUで迎えた朝に戻そう。
ICUは面会時間がかなり限られるので、朝の面会時間のうちに姉夫婦が顔を出してくれる。
昨日の手術日は丸1日病院にいてもらったし、今日も朝早くから病院だ。
姉夫婦にはありがたいやら申し訳ないやらだ。
「ああ、起きてるね。昨日より良さそう」
安心した顔で姉が言う。ありがとう、と答えたが、これまたほとんど声にならない。
姉夫婦はスタッフから「午後には一般病棟に移る」とか「とろみ剤が必要だから売店で購入してほしい」などと言われていたらしい。
午後に一般病棟に移ったらまた来るから、という姉夫婦をICUから見送った。
リハビリをしよう
その日、つまり、ICUを出るときからリハビリが始まった。
体のリハビリ担当のH田さんは30代と見える男性理学療法士だった。(Hさんと書くとH医師と被ってしまうので、H田さんと表記しよう)
優しい雰囲気の人で、近所に住む親切なお兄ちゃん、あるいは部活の安心できて頼れる先輩という印象の人だった。
手術前にリハビリについての話を聞いたときは、手術の翌日からもうリハビリが始まるのかと驚いた。
数日は安静にしているようなイメージがあったからだが、H田さんは言う。
「手術後にICUに入っていたりすると、患者本人ではなく家族からリハビリを止められることがある」
「すぐリハビリをするなんてかわいそう、寝かせておいてあげてほしい」と。
でも寝ているほうが辛いんですよ、とH田さんは続ける。
自分で動けるほうがうんといい。リハビリは少しでも早く始めるほうがいい、そのほうが回復も早い。
手術前に話を聞いていたときはそんなものかと思っていたが、手術後、わたしはH田さんの言葉を身に沁みて実感した。
わたしの場合は手術時間が長く、その間ずっと同じ体勢をとっていたせいもあるのだろうが、体のいたるところが痛くて横になっているのがとても辛かった。
特に首と腰が痛かったのだが、右を向いても左を向いても仰向けになっても痛い。向きを変えているあいだも痛い。
なんとか寝返りは打てたが、体を起こすこともできないし、体にかけられた布団をずらすのも一苦労する。
あの一夜はとてつもなく長く、わたしは呪文のように同じ言葉を繰り返していた。
今が一番痛くて辛い。これからは良くなる一方。と。
横になっているのが辛いのに、横になっていることしかできない。
長い長い夜がようやく明けた翌朝、H田さんがICUにやってきて「体を起こしましょう」と言ったときは、冗談抜きで後光が射して見えた。
体に力が入らないので、体を起こすのも恐くはあったのだが、H田さんに「僕にどさっともたれていいですよ。大丈夫、ちゃんと支えますから」と言われ、思わず胸に飛びこみそうになった。惚れてまうやんけ。
手術翌日は、体を起こしたり、立ったり、支えられながら車椅子に移動したりという動作をした。
立ったり歩いたりに支えが必要というのも初めての経験だ。
手術はこんなに体を変えるものなのかと、うまく動かない体に戸惑いながら思う。

リハビリの最初は立ったり座ったりから
歩くのに支えが必要なのは初めての経験だった
この日は大部屋の横手にあるトイレに行くのにも車椅子を使った。
夜にはひとりで歩けるんじゃないかと思えたのだが、H田さんからひとり歩きの許可が下りていなかったので、看護師が目を光らせていた。ので、トイレに行きたくなったときはおとなしくナースコールをして看護師に車椅子を押してもらった。
さらに翌日には、H田さんからひとりで歩いていいとの許可が出た。
自由にトイレに行ける幸せをしみじみとかみしめた。
手術の翌日(だったか翌々日だったか)からは本格的なリハビリが始まった。
簡単なストレッチをしたり、リハビリルームに作られた通路を歩いたり、階段昇降運動をしたり。
リハビリ初日は、わたしと同じように脳腫瘍の手術を受けたという、同年代の女性と一緒だった。
自分が脳腫瘍になったと知ったときは、ドラマでしか見ないような大変な病気になったとショックを受けたものだが。
こうやって同じ病気で手術を受けた人に会うと、けして珍しい病気ではないのだなと思えた。
その女性は、まだ歩くのも辛そうに見えた。
1日も早く自由に動けるように、お互いにリハビリを頑張りましょうね、と心の中でエールを送る。
これぞ同病相憐れむ、いや、同病相励ましだ。
さらに翌日にはストレッチとマシンを使ったリハビリに移る。マシンはスポーツジムにあるのと同じようなものだ。自転車を漕いだり、ベルトの上を歩いたり、腕や足に負荷を与えて運動したりする。
退院前日まで、少しずつ体にかける負荷を大きくしながらリハビリを続けた。
幸い術後の経過は良好で、退院の前日、最後のリハビリの時にはH田さんから太鼓判を押してもらえた。
2週間前の、体を起こすことすらできなかった自分の姿はすでに遠かった。
遠く思えることが嬉しい、と思った。
顔のリハビリをしよう
体だけではなく、顔のリハビリも行った。
顔のリハビリ担当は、言語聴覚士のK野さん。癒やし系の女性だ。
(しかし、登場人物にHさんとKさんの割合が高い)
元々は顔のけいれんから症状が始まったからか、手術後もわたしの左半面は麻痺が残っていた。
手術直後は、はっきりわかるくらい左の口角が落ちていた。
手術をして日が浅いころ、リハビリの時間にK野さんから何度となく、舌を出してアカンベーをしてください、と言われていて不思議に思っていたのだが、ひとりのときに鏡に向かってアカンベーをしてみたら、自分ではまっすぐに舌を出しているつもりが、斜めに出ていたのに驚いた。
K野さんからは、顔の麻痺を改善するためのマッサージのしかたを中心に教えてもらった。
顔のマッサージがいかに大切かということを、これでもかと説かれた。
マッサージを怠った場合のリスクを詳しく話すK野さんの笑顔がちょっと恐かった。
前にも書いたが、おそらくは手術中に呼吸補助用のチューブを挿入していたせいで、手術後は喉に症状が残り、話したり、物を嚥下したりするのにひどく苦労するようになった。
声ががさがさに嗄れていて、最初の頃は自分でもなにを言っているのかわからないくらいだった。
水分を摂ると必ず噎せた。
さらさらとした水のほうが飲むのには負担が大きいと初めて実感した。
味噌汁だろうがお茶だろうが水分にはとろみをつけないと飲むことができなくて、10日ほどはずっとお茶にとろみをつけていた。
ということをリハビリの時間にK野さんに話したことがあるのだが「喉を鍛える運動をしましょう」と、K野さんはいい笑顔で言ってくれた。
この『喉を鍛える運動』というのがなかなかきつい運動だったのだが、K野さんはいつもいい笑顔でわたしを追い立ててくれた。
いえいえ、すごく感謝してます、はい、本当です。
一般病棟へ移った
話を少し戻して、手術の翌日の午後は、ICUから一般病棟へ移動した。
今度の部屋は、最初の予定通りの4人部屋だ。個室じゃなくなって少し残念なような、個室は個室で落ち着かないのでこれでいいような。
窓側のスペースのひとつに入ることになった。
大部屋の病室で思い出すエピソードがある。
3姉妹の末っ子であるわたしは今回が初めての入院体験だが、2人の姉はどちらも今までに複数回の入院経験がある。
上の姉は4人部屋に入っていたのだが、お見舞いに行ったときに、ベッドを囲むカーテンを全開にしていたことに驚いた。
同室の他の3人は皆カーテンを引いていて、どんな人がいるのかもわからなかったが、その中で姉だけがカーテン全開。
聞けば、昼も夜もカーテンを全開にしていたという。
消灯時、看護師に「カーテンを閉めましょうか?」と声をかけられたが「いいです、開けておいてください」と答えたという。
「カーテンを閉めるとき? 着替えるときだけだねえ、あはは」と笑っていた。
姉は閉所恐怖症でも露出趣味があるわけでもない、たぶん。
上の姉のオープンな性格がよくわかるエピソードだと思われる。
一方下の姉は「安心しておならもできない」と個室に入っていた。
下の姉が入院した病院の個室も一日○円だったようだが(相場は似ているのか、わたしが入院した病院と同額だ)「加入している保険の給付日額と部屋代が同額だから、保険は部屋代にしかならない」とぼやいていた。
それでも個室の快適さを選んだというわけだ。
金で解決できることは金で解決すればいいという下の姉の信念がうかがえて、それはそれで潔い。
下の姉は入院するにあたって、暇だろうからと本を何冊か持ちこんだそうだが、自分の娘から適当に本を選んでもらったそう。
「娘とは本の趣味が合わないからあまり面白くない」と下の姉がいうので、お見舞いに行ったときに一緒に本を数冊差し入れた。
部屋のテーブルに読みかけの、姉の娘が選んだという本が置いてあったので「どれどれ。趣味が合わないという本はどういったものか」と覗いてみた。
ああうん、それ、異世界ファンタジーの本だね。日本人のヒロインが異世界に行ってチート能力を発揮して人々を救うやつだよね。知ってる、わたしも読んだよ。
どうやらわたしと姪っ子の本の趣味は合うようだ。
ここまで書いて思い出したが、わたしは上の姉と本の趣味が合う。というか、わたしが上の姉の影響を受けたのだが。
上の姉が入院したとき、お見舞いに行く前にメールで『なにかいるものある?』と聞いたら『本!』と即答された。『本! 本が読みたい! 本持ってきてえ』と悲痛な叫びが綴られている。
そうとう本に飢えていたらしい上の姉の、作品まで指定されたリクエストで、病室に大量のマンガを持ちこんだ。血は争えない。
わたしの入院に話を戻そう。
手術後は4人部屋の一角に入った。窓側のベッドだったので、外の日差しが入ってくるのは嬉しかった。
入ってみてわかったのだが、この部屋がそういう傾向があったのか、それともどの部屋でもそうなのか、えらく人の入れ替わりが多かった。
入って1週間もすると、わたしは部屋の中で一番の古株になった。
そして常に部屋のベッドはいっぱいだった。午前中に部屋の誰かが退院しても、必ずその日のうちにベッドが埋まった。
少し後の話になるが、自力で歩けるようになると、歩く練習も兼ねてスタッフの邪魔にならないように気をつけながらフロアの中を歩いていたが、やはり他の部屋もいっぱいのようだった。
こんなにいつもいっぱいだと救急患者を受け入れることができないんじゃないかと余計なことを考えたりしたが、実際その通りだったらしい。
なんの事情があるのか退院を渋る患者に、救急車の受け入れを断っているんですよ、とスタッフがやんわり退院を促す場面に行きあったりした。
スタッフの人数もかなり多い。医師に看護師に看護助手、理学療法士、そのほかの人たち。
何十人も立ち働いているが、なんとか顔を覚えたのは部屋を担当してくれた人たちくらいだ。
そして、皆とてもてきぱきキビキビと動いている。
医療現場で働くとはこういうことかと思うくらい、皆がひきしまった顔をしていた。
それでも、患者に向き合うときは一転してにこやかな顔になる。
何人もの看護師やスタッフの人たちと話をしたが、顔を合わせて話をしているときに仏頂面だった人はひとりもいなかった。皆にこやかだった。
自分の表情や言動が闘病中の患者にどういう影響を与えるか、というのを誰もが考えているようだった。
激務の医療現場で働くこと、その働く姿勢に心底頭が下がった。
そして我が身を振り返った。
ああごめんなさいごめんなさい。仕事中に上司の目を盗んで、Yahoo!ニュース見たりしてごめんなさい。でも上司も見てました。
仕事に復帰したら、わたしもわたしなりに頑張ります。
でもちょっとだけYahoo!ニュース見てもいいですか?
一般病棟の大部屋へ移った初日から、さっそくわたしのどたばたは始まった。
〈PR〉


