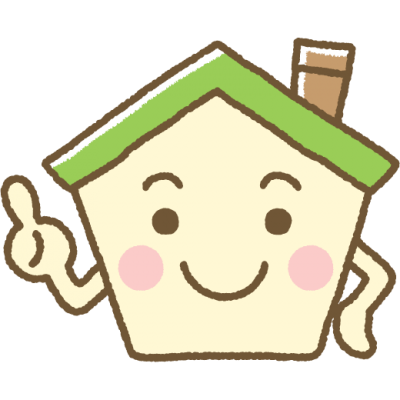
夢見ていた「行きつけの喫茶店」

いつかできると信じてました
学生の頃、夢見ていたことがあった。
社会人になったら、行きつけの喫茶店ができるだろうと。
会社帰りに、昭和の名残があるようなレトロな雰囲気の喫茶店へ行く。
テーブルに座って、好きなコーヒーを注文する。時にはスイーツを一緒に頼んでもいい。
本を読みながら、ゆったりした時間を過ごす。そうして何度も通ううちにマスターと顔なじみになり、席はテーブルからカウンターになる。
イケオジなマスターと会話を楽しみながら1日の疲れを癒やす。
ええ、そんなことを思っていました。
現実は、1日の仕事を終えたらすぐにでも家に帰りたい。ストッキングを脱いでメイクを落としたい。ご飯を食べてお風呂に入ったあとは、部屋着でひたすらだらだらしたい。
かくてわたしに『行きつけの喫茶店』なるものはできなかった。
夢見ていた「行きつけのバー」

きっといつかはできる、かもしれない
20代の頃、夢見ていたことがあった。
もう少し大人になったら、行きつけの小料理屋やバーができるだろうと。
暖簾をくぐり、あるいは重厚な木の扉をくぐり、こんばんは、と言う。
小粋な女将さん、あるいはこれまたイケオジのマスターが、いらっしゃい、と返す。
ああ今日も疲れたわ、とカウンターに座る。
「沖端さん、いつもの?」とおしぼりを出しながら女将さん(あるいはイケオジのマスター)が笑顔で聞く。
ええ、いつものをお願い、とわたしは笑みを返す。
くどいようだが現実は、1日の仕事を終えたらすぐにでも家に帰りたい。ストッキングを脱いでメイクを落として部屋着でだらだら以下略。
かくてわたしに『行きつけのこじゃれた小料理屋(あるいはバー)』はできなかった。
忘れていたわけではないが、わたしはとことんまでインドアだ。
外食するくらいならお弁当を買って帰って家で食べる。
現実の行きつけは
とうとうこの年になるまで『行きつけの店』なるものは持てなかった。
「あちらのお客様からです」とグラスを渡されることもなかった。
沖端の夢見た、照明を片頬に受けながら物憂げに酒のグラスを揺らす大人像ははるかに遠い。
『かかりつけ』はいくつかできた。歯科医院とか内科とか、そんな感じ。
そうして今日もわたしは痛む腰を抱えて、なじみの整骨院の玄関をくぐる。
「せ、先生、いつもの」
「腰痛? まあた沖端さんはこんなに体が歪むまで放っといて。もうちょっとマメに来るようにって言ってるやろ」
い、いでで、痛い、痛いですったら、先生。
