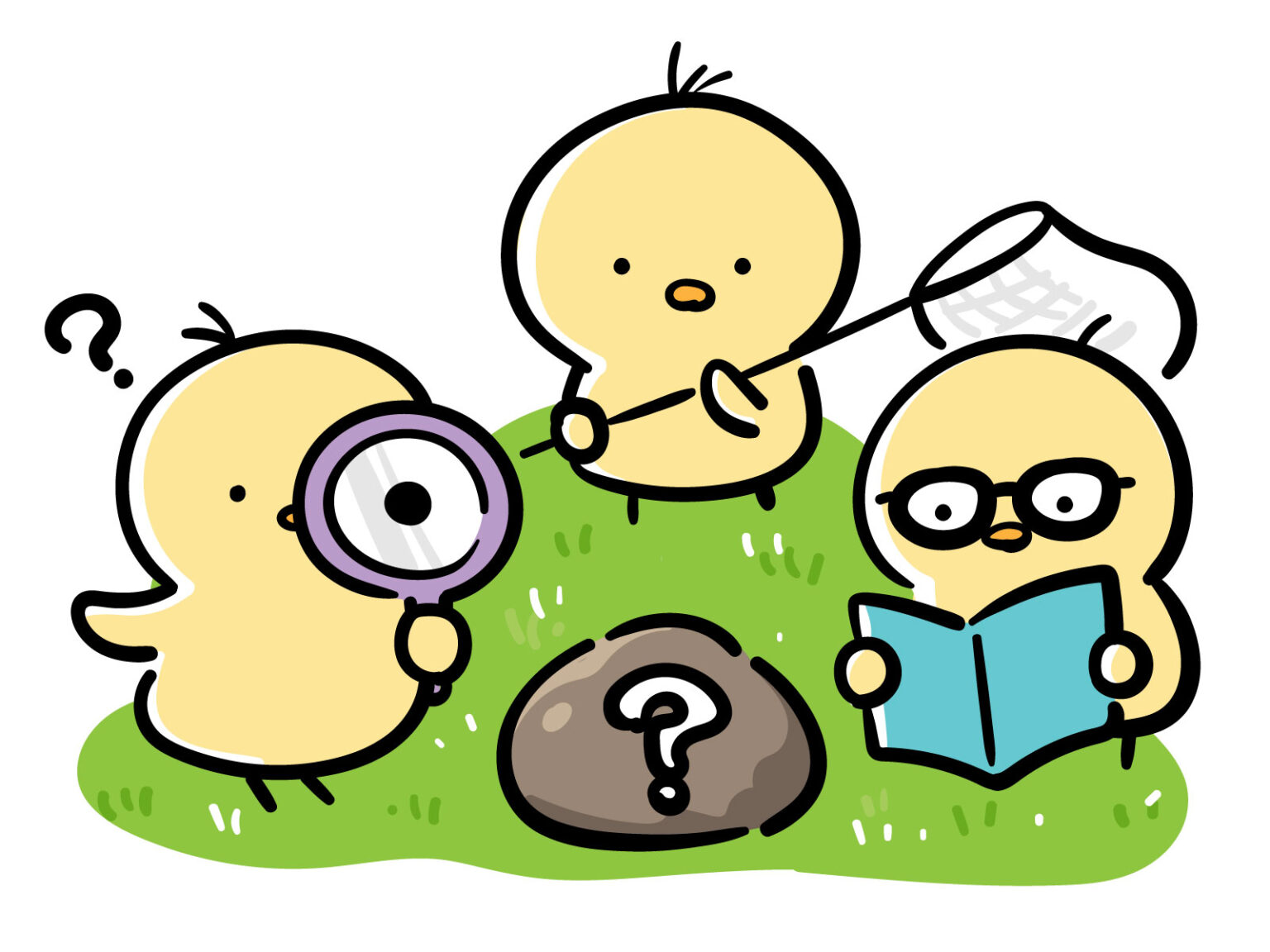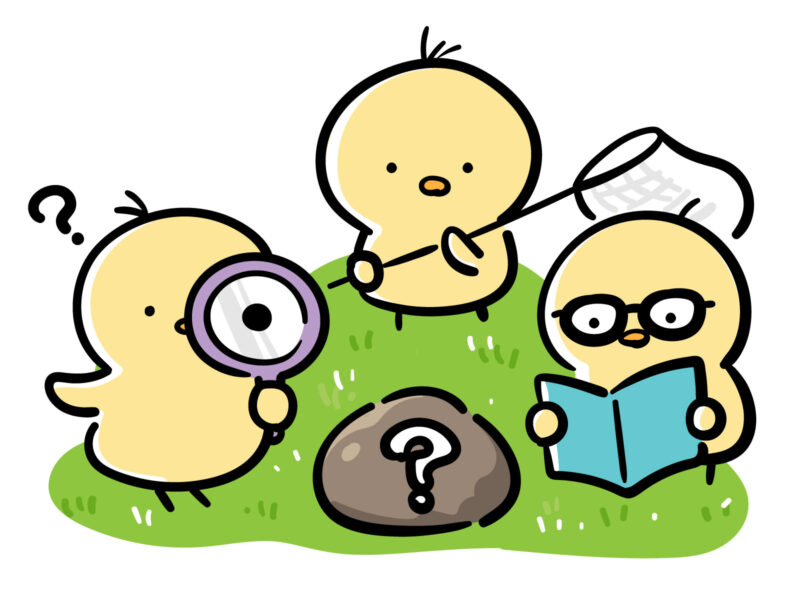
あれは小学校の夏休みのこと

自由研究は自分への挑戦だった
小学校の夏休みには、宿題のひとつに自由研究があった。
今はデパートなんかに、自由研究用のセットなどもあるらしい。いろんな実験ができるようなものがたくさんあるようだ。便利になったねえ。
わたしが子どもの頃にそんな便利なものがあるはずもなく、わたしは自力でなにを研究するかを考えなければいけなかった。
さて、小学校中学年のある夏休みのことだ。わたしは自由研究に『泳ぐこと』を選んだ。
わたしはほぼカナヅチで、泳げない。ちょっと水恐怖症の気があるらしく、水に顔をつけると一気に息苦しさと恐怖感が襲ってくるのだ。
水泳の授業があるくらいなので、小学生の頃はいまよりも泳げたように記憶しているが、それでもヘタな息継ぎで泳げる距離の、せいぜい数メートルくらいだったろう。
その夏、わたしはそんな自分に挑戦することにしたのだ。
『自分への挑戦』が、そのときのわたしの自由研究のテーマだった。(どうだっ)
さんざんな結果だった自由研究
その夏はほぼ毎日、学校のプールに通った。当時はかまぼこ板に自分の名前を書いたものが必要だったので、水泳道具とかまぼこ板を握りしめて夏休みの小学校へ通った。
えんぴつで表を作り、この日は○メートル、次の日は○メートル、と泳げた距離を書いていく。
へたくそなりに息継ぎの仕方を工夫したりもした。
継続は力なりというのか、それともわたしにも根性があったのか、少しずつ泳げる距離は伸びていき、夏休みが終わるころには25メートルプールの端まで泳ぐことができるようになっていた。必死で泳いで、プールの端に手をついた瞬間はとても嬉しかった。
あの夏にわたしは25メートルプールを制覇したのだ。
さて夏休みが終わり、わたしは意気揚々と自由研究を提出した。
だが、クラスメイトの反応はさんざんだった。「なんだこれ、こんなのは研究じゃない」と何人もに言われた。
その時の担任の教師にも「沖端さんが頑張ったのはわかるけど、これは研究じゃないね」と言われた。
わたしが夏休みいっぱいをかけて、自分に挑戦した研究は、誰にも認められなかった。
なぜ評価が高いのか

ぶっちゃけ思いつきです
それから1、2年の後、小学校の高学年になったときだ。
その年の夏休み、わたしは自由研究をなににしようかと考えていた。
その頃父が漁業をしていたのが関係あるのか、食卓にアサリの味噌汁が出ることが多かった。
アサリの貝殻の模様って面白いな、と思ったのがきっかけで、わたしはアサリの貝殻を標本みたいに並べてみようと思いついた。
「アサリ貝の模様はひとつとして同じものがないんだぞ」という父の言葉も自由研究の後押しになった。
空き箱を利用して作った箱に模様と形のきれいなアサリの貝殻を並べて固定し、『アサリのもよう色々』とマジックでタイトルを書いた。
なんせアサリの貝殻は家にたくさんあったので、半日かからずに自由研究の制作は終わった。
夏休みが終わって自由研究の提出をする。
そうしたら、そのときの担任に制作物をすごく褒められた。
ぶっちゃけ思いつきだけの手抜き製作だったわけで、え、これ、褒められるようなものかな、と思った。
なんの間違いか『アサリのもよう色々』はクラスの提出物の中から選ばれて、校内の作品展のようなものにも出されることになった。
あのときにわたしが感じた、当時は言葉にできなかった感情は『釈然としない』というものだったのだろう。