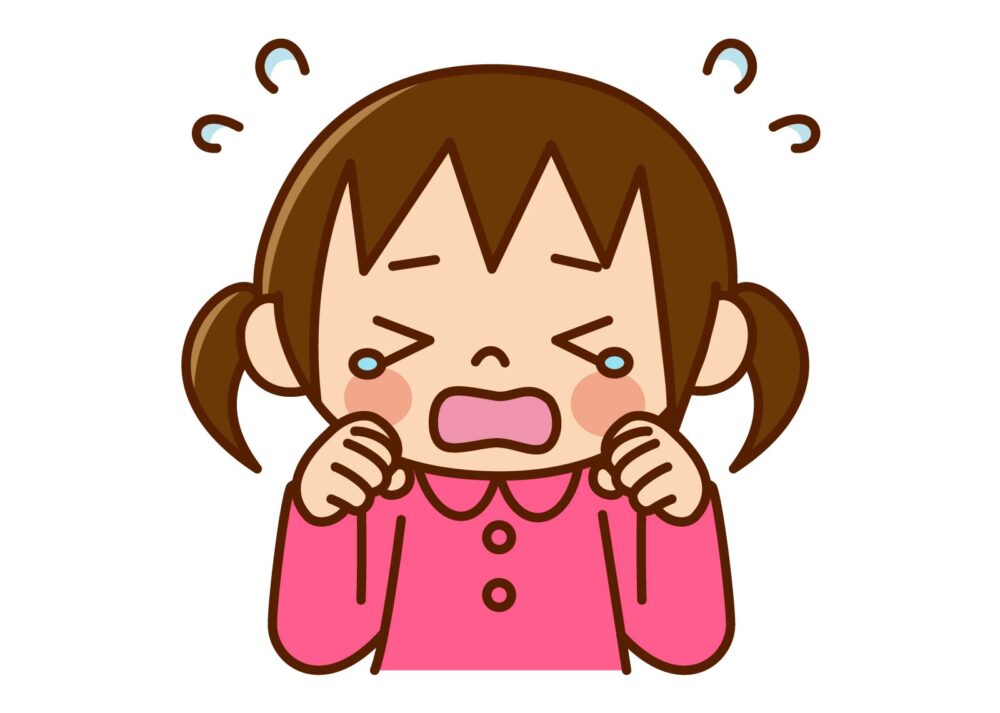
電柱に登ったんですね
これはわたしが子どもの頃に経験した、流血騒動になった痛い話。
小学校高学年のときだったと思う。わたしはその日のお昼過ぎ、電柱に登っていた。ええ、電柱です。
登っていた理由? うーん、そこに電柱があったから?
というのは冗談として。これはかなり恥ずかしい話なので、書くのに少々抵抗がある。いや書くけどね。
わたしの母だが、その頃は近くの会社にパート勤めに出ていた。子どものわたしは家に母がいないことに慣れてはいたが、ときどきそれを寂しいと感じていた。
その日家には姉たちがいた。姉たちは母がいないからといっても特に不満に思うわけもなく、普通にテレビを見ていたと思う。
お昼にいったん食事に戻って、その後再び仕事に出る母を、わたしだけが追いかけてしまった。
パート先は近所だったので、母は歩いて通っていた。遠ざかる母の背中を見ていたのだが、なぜそうしようと思ったのか、わたしは母の背中をもっとよく見ようと、電柱に登ってしまったのだ。我ながら子どもの自分がなにを考えていたのかよくわからない。

もうちょっと考えようよ、子どもの自分
置いて行かれる自分に酔っていたのかもしれない。子どもにはありがちなことだ。
遠くなる母の背中を見送る自分、的なね。
見送るのは別にいいとして、電柱に登る必要はなかったよね。あの頃の自分にそう突っこんでやりたい。
後に怪我をした原因(というか、電柱に登った理由)を母に聞かれたわたしは、仕事に行く後ろ姿を見送ろうと思った、とかなんとか答えたらしい。覚えていないが。
それを聞いた母は、この子がもう少し大きくなるまでパートに出るのはやめたほうがいいだろうかと悩んだそうだ。
おっとちょっと泣きそうになったよ。
でもオカーサン、小学校の高学年って、すでにわりと大きいと思う。
そして滑り落ちたんだ
歩いて行く母の背中はどんどん小さくなり、すぐに見えなくなった。
電柱から下りよう、とわたしは思った。
電柱には左右に足場ボルトがあるので、わたしは慎重にそのボルトを使って下りていった。
電柱のすぐ脇には2段か3段の低いコンクリートブロックの塀があって、コンクリートブロックからは、おそらくは支柱なのだろう、直径1センチほどの錆びた金属の棒が上に突き出ていた。
ああ、なんだか展開が見えてくる。
足場の最後のボルトに左足をかけ、それが最後のボルトだと気づかずに、わたしは右足を次のボルトにかけようとした。それで、ボルトがないもので、足から滑り落ちた。
不運だったのは、滑り落ちた先にコンクリートブロックの支柱の金属棒があったことだろう。
わたしは右の太ももを、金属棒で思いきり擦った、と思った。
痛みはそのときはそんなにひどくはなかった。
いたた、太ももにハデに擦り傷作ったよ、と最初は思った。
そのときは短いスカートを穿いていたので、太ももはむき出しだった。
地面に下りた(というか、すべり落ちた)後で、わたしは擦り傷を作ったとおぼしき太ももに手を当てた。そうしたら、手が見る間に真っ赤に染まった。

太ももがえぐれていたよ
後でわかったが、わたしは右の太ももを金属棒でえぐっていたのだ。
赤く染まった手のひらを見て、わたしはその場にうずくまったまま動けなくなってしまった。
怪我は自覚した瞬間に痛くなるというのは本当だ。
結果は流血。おばちゃんに助けられる
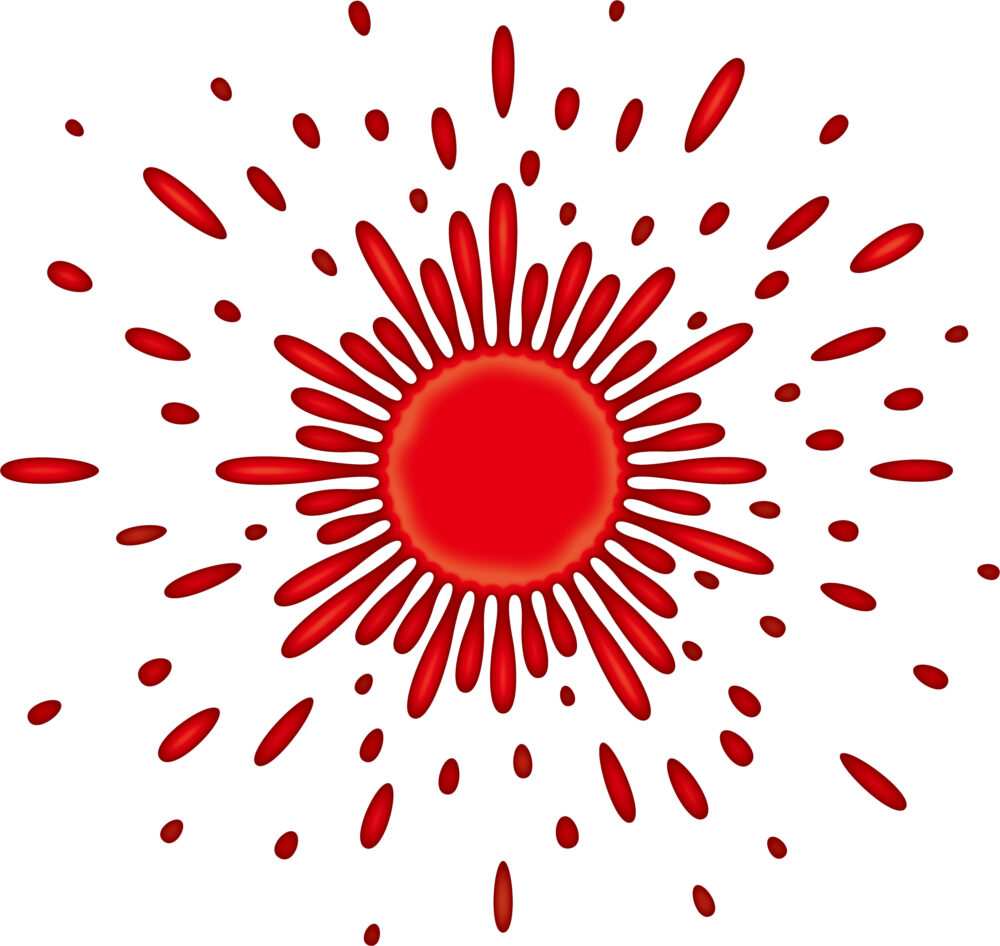
傷って、自覚すると痛くなるよね
足はどんどん痛くなってくる。多分地面には血も垂れていただろう。どうしようと焦っても、動くことができない。自宅からほんの少ししか離れていなかったが、立ち上がることもできなかった。
昼下がりの時間だったが、あいにく田舎なもので、すぐそばの道路には人の姿がない。
ご近所の家から誰かが出てくる気配もない。
どうしようどうしようと思いながら、わたしはうずくまっていた。

途方に暮れるという言葉を実感したあの日
焦りながらもうずくまることしかできなかったのだが、そのときたまたま近所のおばちゃんが通りかかった。救いの女神の登場だ。
母と仲のいいおばちゃんだった。ちょうど我が家を訪ねてこようとしていたらしい。
おばちゃんの娘がわたしの1才年上で、一緒に小学校へ通っていたから、おばちゃんはもちろんわたしのことを知っている。
おばちゃんは電柱のそばの地面にうずくまっているわたしに、最初はにこやかに話しかけてきた。
「こんにちは、アサヒちゃん。お母さんは家にいる?」
「あの、ちょっと前に仕事に行きました」
説明する前に助けを求めろよ、と誰か突っこんでくれないだろうか。
あらそうなの、と返事をしたおばちゃんは、そこでわたしが足から血を流していることに気づいたようだ。驚いて声を上げた。
「アサヒちゃん、どうしたの、足!」
大人から心配されたことで、わたしは気が抜けて泣いてしまった。
小柄なおばちゃんだったが、わたしを抱きかかえるようにして家まで連れて帰ってくれた。
このタイミングでおばちゃんが来てくれて本当に良かった。
家まで戻り、それからおばちゃんなのか姉なのか(たぶん姉だろう)が母の仕事先に電話をしたようだ。
わたしは、布を傷口に当てるとかの応急手当のようなものをしてもらったのだろうと思う。
おばちゃんがわたしの太ももを見て、痛ましそうな声を出したのを覚えている。
「ああ、傷口がえぐれてるね、かわいそうに。アサヒちゃん、見る?」
お、おばちゃん?
いやいや、見ませんよ。
どうでもいいことだけど、田舎のおばちゃんて肝が据わっている人が多いよね。
母の自転車で病院へ。え、麻酔なしで縫うの?
仕事場に電話がきて母は驚いたようだ。すぐに戻ってきた。
とにかく病院へ行かなければということで、仕事着のままの母と一緒に自転車で病院へ行った。
繰り返そう、自転車だ。わたしは荷台に乗せられた。
まあ仕方がない、母は車の免許を持っていない。そのときは家に父はいなかったし、子どもを連れての移動手段は自転車しかなかったのだ。(田舎のおばちゃんにタクシーという選択肢はない)
しかし太ももをえぐった状態で自転車の荷台に跨がるのは大変だったよ。
小学生とはいえ高学年ともなると体格はそれなりなので、荷台に乗せて走るほうも大変だったろうと思う。しかも怪我人だ。田舎のおばちゃんって肝が以下略。
病院に到着した直後のことはよく覚えていない。次の記憶は治療台の上だ。
わたしは治療台に横になっている。
医師がわたしの傷口を縫おうとしていて、子どものわたしはそれが恐くて仕方がなかった。
ほら、お母さんも一緒に体を押さえて、と医師に言われて、わたしは看護師さんと母と3人がかりくらいで体を押さえられた。

麻酔なしだったよ
そして太ももの傷口を縫われた。当時は糸で縫う方法だったが、麻酔なしで縫われたことを覚えている。
当時は子どもには麻酔を使わないというお約束でもあったのか、あるいは皮を縫うのに麻酔はいらないという大胆な考えだったのか。たしか5針は縫ったはずだが、そりゃもう泣き叫ぶほど痛かった。(遠い目)
1週間ほどはまともに歩けなかったと思う。学校はどうしたんだろう?
冬休みとか春休みとかの長期休みの期間だったんだろうか。学校を欠席したという記憶はないから、そうだったのかもしれない。
小学生とはいえ、高学年になって母親にトイレの世話をしてもらうのはとても恥ずかしかった。
そうそう、わたしの太ももをえぐった金属棒の支柱だが、わたしが怪我をした後で、父が折ったか曲げたかしたらしい。
コンクリートブロックの塀は隣の家との境に作られたものだが、勝手に折ったり曲げたりしていいんだろうかと子ども心に心配した。
わたしの太ももには、『つ』を鏡文字にしたような傷が今でも残っている。

