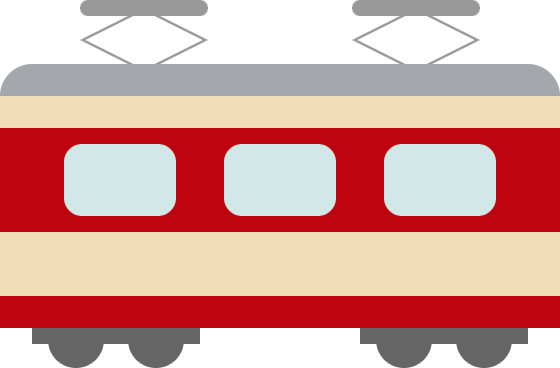
悔しさは想像力で昇華する
誰しも自分の中に天使と悪魔がいるという。わたしにもいる。わたしはそれらに『ホワイト沖端』『ブラック沖端』と名前をつけている。
これはそんなホワイトだったりブラックだったりする沖端が顔を出す話だ。
変態はどこにでもいる。うら若き乙女だった頃は何度か痴漢に遭って恐かったり悔しかったりしたのだが、年を重ねるごとにそんなこともなくなり、その頃はすっかり油断していた。
駅に到着した電車から降り、ホームに出て歩き出した。乗り換えをする乗客や階段に向かう乗客でホームに一気に人が流れる。夕方の通勤時間帯のことで、乗客の顔には疲れが見える。
わたしは階段に向かう流れの中にいた。前方から、乗り換えをする人の流れが来ていることには気づいていたし、その流れの中にラフな格好をした60代ほどと見えるおじさんがいるのにも気づいていた。
そのおじさんとすれ違いざまにぶつかりそうになって、わたしは身を避けた。
おじさんがわたしのほうに顔を向けたかと思うと、いきなりわたしの顔をめがけて息を吹きかけてきた。
まだマスク生活がデフォルトになる前の頃のことで、自分の頬に当たる生温かい息の感触に、ぞわりと鳥肌が立った。
え、今わざと息を吹きかけた?
おじさんとはすでにすれ違っていたが、驚きで思わず振り返った。
そうしたらおじさんもわたしを振り返っており、目が合うと、にやりと笑いかけてきた。
むくりとブラック沖端が身を起こす。身を起こしたところで基本的にヘタれで小心者のわたしのブラックだ。行動に移すことはなにもない。
想像の中で、わたしはおじさんをホームから線路へと突き落とす。ホームに落ちたおじさんは焦った顔であたりを見回す。ホームによじ登ろうとするが、悲しいかなどれほどじたばたとあがいても体力と運動力の不足が原因でよじ登ることができない。
こんなことをしている間に次の電車が来てしまうかもしれない。(田舎だからそんなに早く次は来ないけど)
ねえ知ってる? 電車に轢かれても、すぐには死なないんだよ。
電車の轢死体を検死するとさ、体から飛び出した内蔵や腸に生活反応があるんだって。
あ、生活反応っていうのは、生きている間にできた傷ってことね。
おじさんの焦りと恐怖に歪んだ顔を見下ろして高笑いをする、という想像をして、わたしはなんとか自分を落ち着かせて帰路についた。
ホームに座る少年に声をかける
朝の通勤電車を待つホームで。
電車を待ちながら、わたしは本を読んでいた。周りには同じように電車を待つ通勤客が何人もいた。連れと話をしていたり、スマホをいじっていたり。
その中に小学校の中学年ほどとおぼしき少年がいた
少年はホームの白線を越え、そしてなぜかホームの端に座りこんだ。
両足をホームから垂らしてぶらぶらさせている。
危ないなあ、とわたしは思った。
周囲の乗客に、少年を注意する気配はない。周りに人が多いと、自分が声をかけたり助けたりしなくてもいい、誰かがするだろうという心理が働くそうだが、これもそうなんだろうか。
両足を線路の上でぶらぶらさせている少年に、わたしは声をかけることにした。
これもひとりの大人としての責任というものだろう。
ボク、もうすぐ電車が入って来るから、そこに座ったままでいると両足が飛んでっちゃうよ。
言いかたをなんとかしろ、とわたしの中のホワイト沖端が突っこんだ。
ええ、ダメなの?
しかたないから、ホワイト沖端の添削通りに言い換えた。
「ボク、もうすぐ電車が入って来るから、そこに座っていると危ないよ」
少年はすぐにホームに立ち上がった。
うむうむ、とホワイト沖端がうなずいた。
これも一日一善だね。
シートの上の落とし物
夕方の通勤電車で。駅に電車が到着して、わらわらと乗客が電車を降りていく。
そのときの電車は、壁に沿って長いシートが設置されているタイプだったのだが、わたしは目の前のシートに視線を奪われていた。
その場所にお兄さんが座っていたのには気づいていた
お兄さんが財布を取り出していたのも視界の端に映っていた。
さてわたしも降りよう、とシートから立ち上がったとき、お兄さんが座っていた場所に千円札が落ちているのに気がついた。
周囲を見回すも、当のお兄さんはとっくに電車を降りてしまっている。
目の前に落ちている千円札。なんだろう、以前にも同じようなことがあったな。
数年に1度のペースでお金が落ちる現場に居合わせる気がする。
あなが落としたのは金の斧ですか、銀の斧ですか。
いいえ、あれはわたしが落とした千円札ではありません。
一体わたしはなにに試されているのだろうか。
わたしはハンカチを取り出して、ハンカチで掴むようにして千円札を拾った。
落ちているお金をネコババしているように見えたらどうしよう、と周囲を伺ってしまうあたり、余計怪しい行動になっている。
電車の扉を出たすぐ近くに駅員さんが立っていた。
よかった、ブラック沖端が唆さないうちにさっさと手放そう。
わたしは駅員さんに、すみません、と声をかけた。これがシートの上に落ちていました。
駅員さんは、おや、という顔になる。
「ハンカチですね。あれ、ハンカチにお金が挟まっていますね」
いえ、落ちていたのはお金だけです。このネコ柄のハンカチはわたしのものです。なんとなく素手で触りたくなかったもので。
千円札を受け取った駅員さんは、
「拾得物の届け出はどうされますか」とわたしに聞いた。
あれですか、どのくらいの期間か持ち主が現れないと自分のものになるという。
「いえ、結構です」
おほほ、大人の女性ですからね。
そんなことにこだわらないのですよ。これも一日一善ですわね。
わたしは信じている。
いつか電車の精が、わたしに金のもふもふと銀のもふもふを贈ってくれることを。
